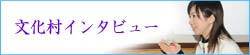日本一になった「道祖神納豆」のルーツを探ろうと訪ねた安曇野。のどかな田園風景に雄大な北アルプス、澄んだ湧水・・・。とにかく空気がおいしい!
北アルプスを借景にした、豊かに広がる田園風景を楽しみながらの道祖神めぐり。それぞれを注意深く見てみると、彫刻の種類や表現の内容などバラエティに富んでいて、一つ一つの道祖神のこだわりが見え隠れして、その個性ある奥深さに心躍りました。
安曇野の道祖神には双体道祖神が多く、握手しているものや肩を組んでいるもの、酒を酌み交わしているものなど仲睦まじい物がたくさん! 多種多様な表情はどれも豊かで、安曇野の原風景に融和しています。
村田商店さんでは自社の特色、長野の特徴をきちんと出したいという事から、原料選びにこだわっている点や、何よりも購入するお客様の声を大切にして納豆づくりをされている、本物の納豆職人さんの心意気と真摯さを感じました。
道祖神納豆のラベルには五穀豊穣という願いを込めてその4文字を入れたとお聞きしましたが、道祖神は様々な願いを引き受けてくれる庶民的な神様なので、健康や長寿など、納豆を食べることで期待されるいろいろな効果も願掛けできる事まで含めて、まさにぴったりのネーミングだと思いました!
道祖神は村人にとって、無病息災、子孫繁栄、五穀豊穣などを祈願した路傍の神でした。集落の境や村の中心、道の辻や三叉路などに多く見られるように、悪霊や悪い病が村や集落へ入るのを防ぐ庶民の守り神でした。
庶民の生活をしっかりと見つめてくれていた道祖神。
そんな道祖神の心を包み込んで、庶民派のこだわり納豆を作り上げた村田さん。今までの高級こだわり路線と合わせたラインナップは厚みを増しました。
原料や資材に糸目をつけなければ高級なこだわり納豆は出来るけれども、もっと手が届きやすいこだわり系の納豆は、村田さんが今まで積み上げてきた、こだわりノウハウの蓄積があったからこそ生み出す事が出来た。
でもこの必然は・・・
道祖神さまのみが知り得べきことかも知れません。
前半は安曇野ブランド推進室と観光協会さん → こちら
|
松尾芭蕉の「奥の細道」の序文に以下のくだりがあります。「道祖神のまねきにあひて、取もの手につかず・・・」
旅に出ようと思ったら、そぞろ神が乗り移って心を乱し、おまけに道祖神の手招きにあっては、取るものも手につかない有様・・・
旅に出る理由として、道祖神の手招きにあった。道祖神に招かれるがままに芭蕉の旅は始まったようですが、私には道祖神さまからの手招きは特にありませんでした(笑)
芭蕉の時代に既に定着していた道祖神。今回安曇野で道祖神巡りをしてみて、村人たちの暮らしにしっかりと根付いていた庶民文化がしっかりと継承されている事に感心しました。
いくつか道祖神をまわらせていただいた中で麻生が一番印象に残ったのは「常念道祖神」。二本の桜の木の間に道祖神と常念岳。まるで額縁のような役割を果たし絵画のように見えて、とっても素敵でした。
桜が咲く時期にも是非訪れてみたいし、サイクリングしながら道祖神めぐりもしてみたい!
安曇野・・・
絶対また行きますね!
好きです、安曇野。
待ってて、道祖神!
納豆文化村:沢口麻生
|
|